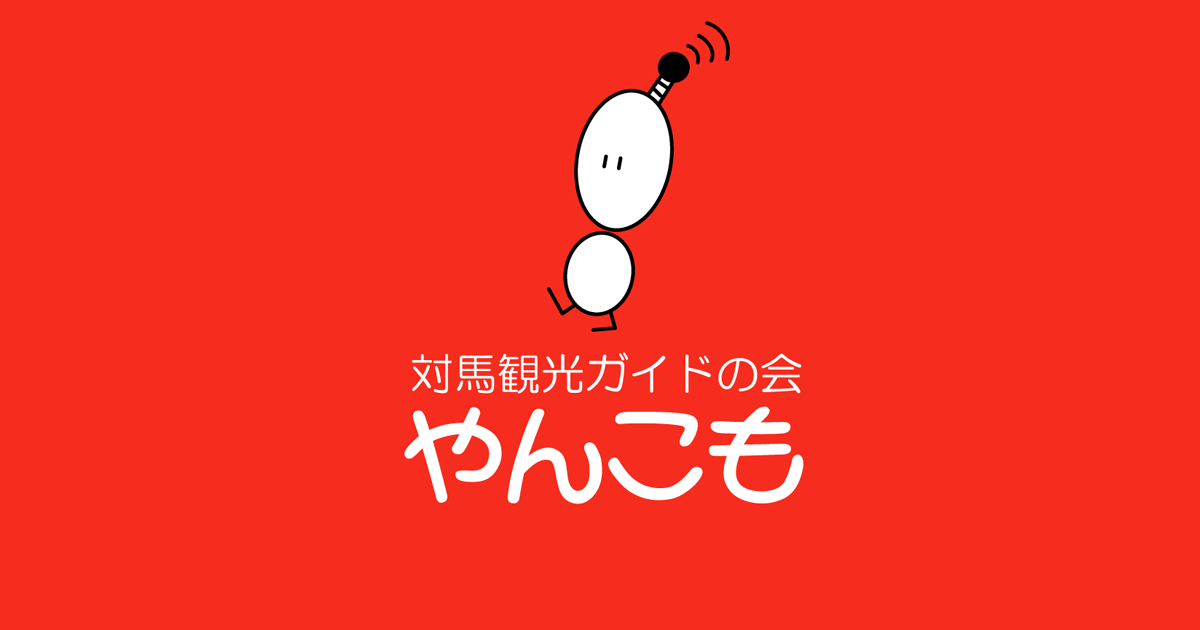
「対馬観光ガイドの会やんこも」研修・熊本県宇土市/熊本市
こんにちは、観光担当Nです。
2011年9月24日(土)~25日(日)、「対馬観光ガイドの会やんこも」の熊本研修旅行を行いました。
今回の研修は、初代対馬藩主・宗 義智(そうよしとし)とゆかりの深い小西 行長(こにしゆきなが)と加藤 清正(かとうきよまさ)について学ぶことが目的です。
清正・行長・義智のマメ知識
- 加藤 清正、小西 行長、宗 義智は、豊臣秀吉・徳川家康の時代を生きた戦国武将。
- 行長は商家出身で熱心なキリシタン、清正は秀吉子飼いの武将で日蓮宗門徒など、まったくタイプが異なり、合わない。
- 秀吉は、この2人に肥後(熊本)を2分して統治させ、競わせた。清正は、土木治水・築城・農業政策などで人心をつかみ功績をあげるが、行長は宇土城築城に際し天草衆と戦いになるなど苦労する。
- 朝鮮出兵(文禄慶長の役)に際し、行長は娘マリアを義智に嫁がせ、対馬宗家との関係を深める。義智はマリアのすすめでキリシタン(洗礼名ダリオ)となる。
- 朝鮮出兵において、清正は秀吉の希望通り猛進したが、行長は秀吉を欺いてでも和平を実現しようとして、敵の策に陥る、偽の使者を仕立てようとするなど失策を重ね、秀吉に死を命じられる(のち助命)。
- 秀吉の死後、関が原の合戦が勃発し、清正は東軍(家康方)、行長は西軍(石田三成方)につく。敗れた行長は、キリシタンであったため切腹(自殺)ができず、処刑され、領地は清正に与えられる。
- 義智は、秀吉には朝鮮出兵の第一陣を、家康には戦後の和平交渉を命じられる。自身もキリシタンであったが、関が原の合戦後に妻マリアを離縁し、キリスト教も棄教。和平交渉の成功を家康に認められ、初代対馬藩主になるなど、激動の人生を送った。
- 離縁後、マリアは長崎に送られ、そこで生涯を終える。
- 加藤家は、清正の子の代に謀反の疑いをかけられお家断絶となるが、後をついだ細川家は加藤家を非常に尊重した。
- 清正は今でも熊本の英雄で、名城・熊本城は熊本のシンボルであり、最大の観光資源。
三者三様の激動の人生ですが・・・
- 清正は猛将・築城の名手・虎狩り伝説などで人気があるが、行長は戦下手・打算的なイメージが強く、いまいち人気がない(-_-;)
- 宇土市教育委員会では、地域の偉人・行長の顕彰事業として講演会や現地ツアーなどを行っている。

1日目は、06:45厳原港発のジェットフォイルで博多まで2時間15分、九州新幹線で博多駅から熊本駅へ約40分、JR鹿児島本線で熊本駅から宇土駅まで11分。
宇土駅に降りたものの、観光看板・案内図などもなく、小西行長のイメージは特に感じられず・・・。

駅から少し歩くと、行長が整備した船場がよい状態で残っていました。

宇土市の講演会では、優れた水軍の将で商才もあるが、キリシタンであるがために政権中枢に居座ることができず、また秀吉の家臣であるためにキリシタン弾圧に加担しなければならないなど、矛盾と苦悩に満ちた行長の生涯を身近に感じました。

PRキャラクター「宇土ん行長しゃん」の発表も(^_^;)

講演会の後は、近世小西城へ。行長が整備し、死後は清正が隠居所として普請しましたが、島原の乱後に徹底的に破却されています。
行長像が西の空を見つめていました。

翌日は清正が築いた天下の名城・熊本城へ。3連休の最終日ということもあり、観光客も多く、武将お出迎え隊?も大人気。
清正が築いた石垣の重厚感に圧倒されました。行長と清正の人気の差にもびっくりしましたが・・・(-_-;)

清正が眠る本妙寺へ。もともとは清正が父のために大阪に建立、熊本城に移され、清正死後に現地に移りました。

山頂にはまさに武神!といった雰囲気の清正像が・・・。
製作は、長崎の平和祈念像で有名な北村西望(きたむらせいぼう)ですが、戦中の金属供出で失われ、戦後に再建したもの。

そして、今回一番のサプライズがこれ。
本妙寺には隣接していくつも寺社がありますが、東光院というお寺の説明看板に「小西行長ノ墓碑」の文字が。
行長処刑後、家老(日蓮宗信徒?)が招来したそうです。
ちなみに行長の娘マリアは、対馬市厳原町中村の八幡神社内に祭られており、親子ともども「異教」の墓所にも祭られていることになります。
熊本の観光資本はすべて熊本城(清正)に投入されているような充実ぶりで、観光面では完全に清正に軍配が挙がっていましたが、対馬の殿様(初代藩主)の義父・行長について学ぶことができ、充実した研修旅行となりました。


 https://kacchell-tsushima.net/?p=1947
https://kacchell-tsushima.net/?p=1947



