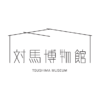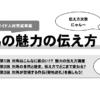「光る君へ」刀伊の入寇と対馬について
こんにちは、大河ドラマ「光る君へ」(12月1日放送・第46回)で、平安時代最大の外寇事件とされる「刀伊(とい)の入寇」が描かれ、ドキドキしているエヌです。
今回は、この事件で英雄となる藤原隆家(竜星涼さん)が髭をたくわえた快活な逞しい姿を見せ、オリジナルキャラの周明(松下 洸平さん。対馬出身という設定)が再登場し、また双寿丸(伊藤健太郎さん)が武者として刀伊と戦う姿が描かれました。
壱岐や対馬を襲い、博多に襲来した刀伊(女真族)の集団に襲われ、海岸を逃げ惑う紫式部と周明、そして衝撃の結末へ!
(↓このサムネイルはダメでしょう・・・)
で!
ドラマではほとんど描かれなかった対馬の状況について書きたいのですが、その前に、刀伊の入寇の概要についてはこんな感じです(雑っ)。
刀伊の入寇
概要としては、
- 寛仁3年(1019年)、50隻3000人とされる賊の集団が対馬・壱岐・筑前・肥前を襲い、大きな被害をもたらしたが、藤原隆家と九州の武士団により撃退された。
- 賊の正体は刀伊=女真族(じょしんぞく。のちに中国東北部に金、また中国全土で清を建国する部族。満州族とも)であった。
- 賊は日本撤退後に、朝鮮半島で高麗水軍により撃退され、拉致されていた日本人約300人が高麗により日本に送還された。
- 朝廷の危機意識・反応は鈍く、隆家は私財により高麗の使者に報いたとされる。
対馬の被害
- 対馬の被害は、殺害36人、拉致346人(男102人・女・子ども244人)、国司対馬守遠晴(姓不明)は脱出し大宰府へ逃れる。
- 物的被害としては対馬銀山の焼損。
ということなのですが、
「辺要 壱岐対馬防人史」(小松津代志)によると、対馬の守・遠晴が隆家に報告した内容は、
- 賊は50隻、船の長さは8~12尋(1尋は約1.8m)、1隻あたり30~40の櫂を使用し、50~60人が乗船しており、全体では2500~3000人程度とみられる。
- 100人が1単位部隊。前衛20~30人が刀を振りかざして突入し、残り70~80人が弓・楯を装備した主力で、20隊が編成されている。
- (対馬では)まず銀山が焼かれ、殺害18人、拉致116人。
- 上県郡では殺害9人、拉致男女子ども132人、下県郡では殺害107人、拉致男女子ども99人。
- 賊に食われた牛117頭、馬82頭、計199頭、焼かれた家45軒。
とのこと。
長嶺諸近(ながみねのもろちか)の物語
対馬判官代・長嶺諸近は、家族とともに刀伊に拉致され、いったんは脱出したものの、家族のことが心配で高麗に密入国しました。
賊の正体や日本人の消息を確認し、大宰府に報告しましたが、母・妻はすでに殺害され、生き残っていたのは伯母だけでした。
貴重な情報を伝えた諸近でしたが、渡海の禁を破ったとして禁固刑に処せられ、その後の消息は不明です。
「アンゴルモア元寇合戦記」(対馬の元寇を描く漫画・アニメ)に、防人の末裔「刀伊祓(といばらい)」のリーダーとして登場する長嶺判官は諸近の名を受け継いだ、という設定です。
外寇の標的となった対馬銀山
刀伊によって焼失したとされる対馬銀山は、対馬の南西部・厳原町佐須(いづはらまちさす)地区にあり、7世紀に開発された日本最古の銀鉱山(日本書紀)でした。
元寇の際にも、蒙古・高麗軍は佐須浦に侵攻しており、断崖絶壁が多いという地形上の問題だけではなく、銀山が狙われた可能性もあります。

※佐須の鉱山は後世に再採掘されているため、写真は、より原形を残している厳原町阿連(いづはらまちあれ)の鉱山跡です。
外寇と外征と対馬の歴史
刀伊の入寇では、藤原隆家や武士団の奮戦により賊の撃退に成功しますが、朝廷の危機意識は薄く、やがて訪れる武士の時代の幕開けを告げる事件でした。
刀伊の入寇に限らず、国境の島・対馬は常に外寇と外征の緊張にさらされてきました。
白村江の戦い(7世紀)は、中央集権国家「日本」が誕生するきっかけとなりました。(対馬に金田城が築かれ、防人が派遣される)

元寇(13世紀)は、奮戦した武士に対して恩賞(土地)を与えることができず、鎌倉幕府崩壊の原因となりました。(対馬の守護代・宗助国一党は蒙古・高麗軍を相手に全滅するまで奮戦)

文禄慶長の役(16世紀)は、豊臣政権の崩壊(徳川家康による天下統一)を引き起こしました。(対馬の宗氏は文禄慶長の役に加担し、のちに家康の命により和平交渉を行う)
国境の島・対馬が舞台となる外寇と外征の事件は、常に、日本という国の形が変わる時代の転換点であり、対馬の歴史は日本の外交史そのものだったのです。
対馬の歴史の現場を歩き、この国の歴史のターニングポイントに触れてみませんか?
(まとめ方、強引!)


 https://steranet.jp/articles/-/3810
https://steranet.jp/articles/-/3810